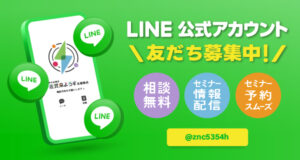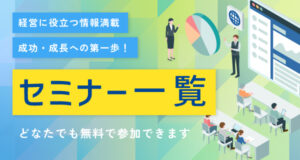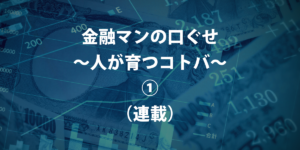池田 巧
佐賀よろず支援拠点、コーディネーターの池田巧です。
異質の世界とも揶揄される「金融業界」ですが、数多くの企業経営者・従業員と接することができ、商工会議所や商工会等の支援機関の方々とも関わりがあります。また、上司や同僚から学ぶことも多く、地域において、これほどにバラエティに富んだ接点や経験を持てる職業は少ないといえます。
迷ったり、悩んだりしたとき、上司や同僚から口ぐせのように(時には、耳タコのように)伝えられるメッセージは、自分を変えるコトバや育ててもらったコトバとして、自分の引き出し(経験や事例)が増え、また人のぬくもりのある(心動かされる)シーンの連続です。
このブログでは、中小企業支援に真摯に取り組む金融マンが、日常の仕事の場で頻出のコトバを通じ、企業経営者の目線でも捉えながら、また人が育つコトバとして掲載します。
(注)当職の所属する(した)支援機関の見解や方針を示すものではありませんので、ご理解のうえ、一読いただけますことをお願いいたします。
人手不足感の高まりは、金融業界にも広がる
今、人口減少や少子高齢化を背景に全産業的に人手不足感が生じています。令和5年度の平均有効求人倍率は1.29倍(求人数/求職者数)と高止まりが続き、また、女性の就業者数は同年度3059万人と過去最高を記録しましたが、人手不足感は一向に改善されません。
この人手不足感は、金融業界にもおよんでいるといえ、「日本の中小企業は減少↘、金融マンも減少↘」しています。
日本の企業者数は、21年337.5万社(14年比△11.6%)、この7年間でも1割以上も減少しています。なお、2000年4月当時の中小企業者数は484万社であり、20年間で約150万社減少しています。

この同じ期間における金融マン(銀行員数・信用金庫職員数、以下「金融マン」という。)は40.1万人から37.9万人に減少しています。金融機関の合併等による統合や店舗見直し等が進むほか、フィンテック等による業務のIT化が進展したことも一因といえます。

金融マン1人あたりの小規模企業者数は、8.11社から7.53社に減少しており、一人の担当者がフォローする企業者数が減ることは、裏を返せば、小規模企業者にとって、手厚い支援が期待できる(歓迎すべき))数値に見えます。
インターネットバンキングの進展やATM設置のコンビニが増え、顧客が金融機関の店舗に行く機会は減っており、その空いた時間を使って、支援を必要とする中小企業や事案に金融マンのマンパワーを配分されることを期待しますが、金融機関には、預金や融資の仕事以外に保険や証券等の販売のほか、現在は、地域振興・活性化のためにも人員を配分しています。
さらに、店舗統廃合による人員減を兼ねた業務効率化は、一人の担当者でカバーすべきエリアや企業数が増大している側面もあります。
併せて、働き方改革等で昼休みを導入する店舗や残業抑制・有給休暇促進等の働きやすい職場づくりもあって、個別企業を支援するための時間が総じて減少しているといわれています。


「人に育てられ、人を育てるコトバ」
仕事に限らず、多くの人と日常的に接して感じる共通の思いは、『良くありたい』ということです。それは、「相手のためになる、社会のためになる、自分のためになる」といった置き換えができ、それは貢献意欲・承認(帰属)・自己成長(自己実現)の欲求ともいえます。近年は、コンプライアンス(法令遵守)が重視され、ミスや不正が生じた場合、仕組みやマニュアルはどうだったのか、マニュアルに問題がなかったのかと...
少子高齢化、円安、物価高騰、激甚災害など、数年先が予測できない「不確実性(VUCA)の時代」の事業経営は難度が高く、つまり、経営者が一人では最適解を出し難い時代ともいえます。このことは、金融マンにも同じようなことがいえ、最低限の手順が示されたマニュアルあるいは細かすぎた(ガラパゴス化した)マニュアルどおりに解決を試みようとすれば、ジレンマに陥ったり、マニュアルにはない盲点に気づかないこともあります。
かたや、「AIが教えてくれる」、「AIが答えを導き出してくれる」などの風潮もあって、我々自身が「何でも便利になったこと」をいいことに、「めんどくさい」、「わずらわしい」といって、「思考を停止」あるいは「思考を放棄」すること奨めているともいえます。
AIやロボットの活用で効率かつ合理的な最適解を導きやすくなることは確かですが、AIは、覚悟や責任を取りません。自分の行動やその結果は、自分が取るしかありません。
金融マンが、顧客を訪問する時間や対話する時間は、確かに「コスト」ですが、誰しも『良くありたい』と願い、日常の仕事をこなしています。「コスト」をかけてでも顧客に会い、顧客の声に耳を傾ける姿勢や行動は必要ですし、まだ、確かな数字にはあらわれていない内外環境が生じています。金融マンにも、その時々の自分の置かれた状況や心持ちと出会い、迷ったり、悩んだり、あるいはモヤモヤとした心を抱えます。
そのようなときに道筋(目途)がついてやる気が出たり、苦境を乗り越えて自分が成長できたり、難局を突破できた背景には、往々にして、「人に助けられた」、あるいは「人に育てられた」といった事例や経験が積み上げられています。
仕事は、選択と覚悟の連続ですが、そこには、上司や同僚から仕事の場で発せられた具体的な「コトバ」があり、多くのエピソードがあります。
「人に育てられ、人を育てるコトバ」が、仕事への向き合い方を教えてくれた、顧客との向き合い方として、今もなお、脈々と引き継がれています。経営者のそばにいてくれるはずの金融マンは、きっといます。ただ、経験が少なかったり、まだ、気づいていないだけだと私は思います。
「なんに、いくらいるんだ!」
◆資金使途と資金効果 ◆必要金額 ◆必要時機
融資業務をやっている金融マンには、誰しも経験のあることですが、企業経営者から次のような問いや投げかけを受けることがあります。
・「うちは、いくらまでなら借入れできますか?」
・「いくらでもいいから貸してほしい!」
・「銀行は、どうせ貸さないでしょ!」
・「うちの融資限度額はいくらですか?」 など。
融資業務の件数をこなしていますと、上記のような質問に対して、つい、以下のような考えが先に立ちます。
【返済可能額】
これまでの損益計算書に記載された営業利益や経常利益、減価償却前利益をベースに、既往借入金を踏まえて、有利子負債の償還可能年数を試算します。
お客さまの問いに答えるため、あるいは答えることのできる金融マンとしての顧客からの信頼を勝ち取りたいと考えることがあります。その際、個々の企業の調達能力を見立てることがあります。


まさか、そんなことあるのと思う方もいらっしゃるでしょう。
金融マンであれば、「古くて新しく」、「新しくて古い」、いわゆる普遍的なことであり、上司や同僚と対話をしていれば、そもそも論として話すこと頻繁にあります。
融資には、資金供給機能・ 信用創造機能があります。また、金融機関の重要な存在意義は,資金の受入れ(預金等)と供給業務(融資等)を同時に行うことにより, 社会的な資金仲介機能を発揮しているといえます。
その融資には、①安全性の原則,②収益性の原則,③成長性の原則,④公共性の原則,⑤流動性の原則といわれる基本原則「融資の5原則」があり、いずれの原則に重点をおくか,優先順位をどのようにするかは、個別の案件 により異なります。ある金融系ドラマでは、「融資の要諦は回収にあり」という金融マンが発するシーンもあります。
話しを戻しますが、
上司からの先ほどの問いに即座に返答できない金融マンがいます。
お客さまのことを知ろうとすれば、「うちは、いくらまでなら借入れできますか?」や「うちの融資限度額はいくらですか?」 に対し、
「事業経営の何にご入用ですか?」【資金使途】
「そのご入用には、いくら必要で、そのうち借入希望されるのですか?」【必要金額】
「どの資金は、いつまでに必要ですか?」【必要時機】
「その資金を投じる効果はどのように試算されていますか?」【資金効果】
のようなインタビューやヒアリングがなされるべきです。
つまり、いくら借りられるか(融資できるか)ではなく、何にいくら必要なのかという原理原則的なやり取りです。
近年は、融資のクレジットスコアやモデリングシステム等でAI自動診断の補助機能が進化・向上しています。また、目先の仕事に追われ、つい、何でもかんでも省きたくなってしまいます。
設備資金にしろ、運転資金にしろ、企業の置かれた現状を知ったうえで、社長は、借入調達して、どのような事業展開を描こうとされているのか。限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ)をベースとし、よりベターな、あるいは戦略的な経営判断をされているのか確認する必要があります。社長(企業)側にも未知あるいは盲点な部分があったり、迷ったり、悩んでいることがあるかもしれません。余もすれば社長は、そんなことを相談してもいいのか、そんな初歩的なことを聞いて経営能力を疑われやしないかといったことを心配している場合もあります。
融資業務になれると、ややもすれば、融資ありきで話しをすすめたり、必要なことをショートカットして、話しを進めてしまい、経営者と金融マンとの間でボタンが掛け違えたような状態にも陥ります。
人が育つ瞬間

この上司のコトバに、フッと原点に立ち返ったり、そもそも企業に関する事実(ファクト)を掴んでいないことを痛感し、さらには、無意識的に融資ありきで自分に都合の良い判断材料ばかりを集めていたことまであります。
このようなことは、金融業界だけに限りません。あらゆる業界の誰しも(経営者も従業員も)、忙しい毎日に追われ、成り行きで物事を進めてしまうこともあって、「なんのため」、「だれのため」といった、そもそも論をスルーして処理していることがあります。
私も然り、この金融マンの口ぐせに、何度、自問自答を繰り返し、何度、客観視する機会を創ってもらえたか。このことを「枚挙にいとまがない」というのかもしれません。この数多い機会が、自分を成長させてくれたり、顧客本位の姿勢をつくったり、ひいては、働きがい(やりがい)までも感じることに繋がったことは言うまでもありません。
さいごに
経営者の傍には、顧問税理士や金融マンが存在します。まさに、「餅は餅屋に聞け」ということですが、ワンストップで完結的に解決できる支援者は存在しません。多様性があたりまえの時代、予測困難な時代といわれ、誰に聞いても、誰に相談しても迷いや悩みが快晴のように晴れることはないですが、そもそも論に立ち返って、思考を整理する(体系的に整理する)ことも大切となります。今、いろんなメディアで、パーパス経営が必要といわれることも、このような時代を受けてのものと私は考えます。
経営者も金融マンも働く人にとって、考える時間は、決して無駄ではありません。付加価値を生むための有益な時間にすればよいのかもしれません。無論、思考のうえでの案ずるより産むがやすいしも時に必要です。
佐賀県よろず支援拠点では、事業者のみなさまからの様々な悩みや相談に対応しています。企業ごとに悩みも課題も十人十色です。多様な課題に応じた専門家(コーディネーター)がいて、経営者とともに汗して、考えます。 無料で何度でもご相談いただけますので、お悩みの方は是非、ご利用ください。