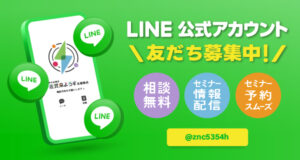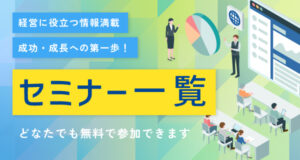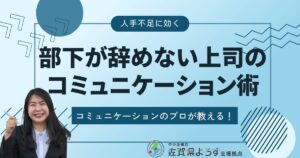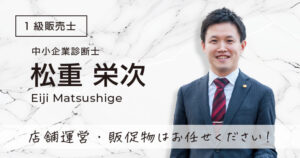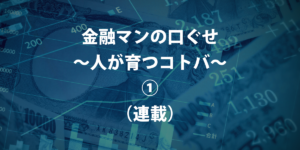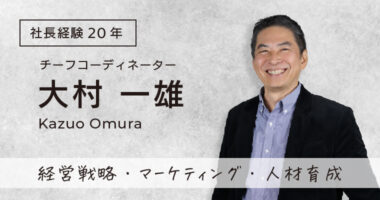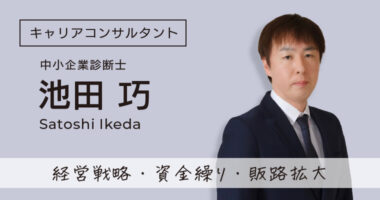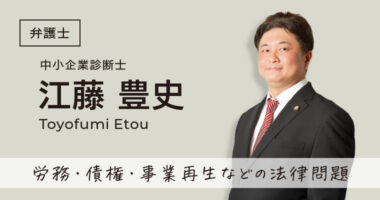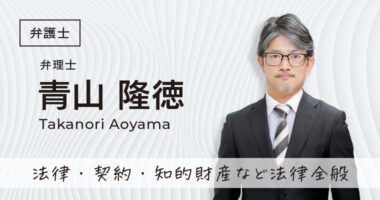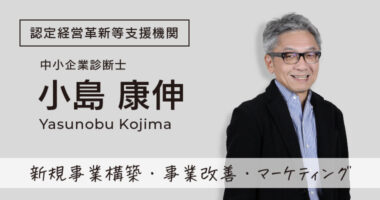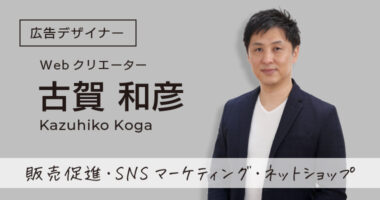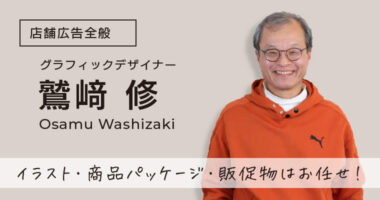全国で多くの企業が人手不足に苦しんでいる現在。「社員がなかなか定着しない」「いい人が入ってもすぐ辞めてしまう」といった悩みを抱える経営者の方もいるのではないでしょうか。
今回は、人材育成とコミュニケーション領域を専門とする、佐賀県よろず支援拠点コーディネーターの北村朱里が、部下が辞めない上司が身に付けている4つのコミュニケーション術についてお伝えします。
1:褒める
「部下を褒めるのは苦手だな」「最近、褒めていないかも」という上司の方の声を聞くことがあります。これはある意味しかたないことかもしれません。もし部下が悪いことをしたのであれば上司が何も言わないわけにいきませんが、良いことは特に伝えなくても当面の業務に支障はないからです。そのため、どんどん褒めることの優先度を下げてしまい、そのうち褒め方もわからなくなってしまうのでしょう。
一方、部下と良好な関係を築いている上司の方を見ていると、頻繁に部下を褒めていることがわかります。本人の成長や会社の未来を考えたときに、褒めることは重要だとよく知っているのです。
人を褒めることは「良いところを見つける」「それを伝える」の2つのプロセスで構成されます。この2つができるようになれば、誰でもすぐにでも褒め上手になれるのです。
良いところを見つける方法
良いところを見つけるには「その人のことを深く知らなければならない」「付き合いが長くないと無理だ」と難しく捉えられがちですが、実はそんなことはありません。仮に今日入社したばかりの新人であっても、良いところを見つけるのは十分可能です。
その方法とは、相手の「行動」に着目すること。例えば「この人はいつどんなときでも落ち着いている」といったその人自身の良いところは長い付き合いにならなければ把握できないかもしれませんが、「さっき突然お客様に質問された時、落ち着いて回答していた」という行動の良いところであれば、接客をしているその瞬間さえ見ていればわかります。
まずはその人のすべてを知ろうとせず、行動を見て何が良かったかを認識することから始めてみてください。そうした積み重ねで、その人自身の良いところもゆくゆくわかっていきます。
良いところを伝える方法
「さっき突然お客様に質問された時、落ち着いて回答していましたね」のように、あなた自身が見ていて良いと思った事象をそのまま伝えるだけでも十分です。さらに「さっき突然お客様に質問された時、落ち着いて回答していましたね。すごいなと思いました!」というように自分の感想や感情も付け加えると、相手との距離をぐっと縮められます。
大事なのは「このくらいのことはできていて当たり前だから、わざわざ言うほどのことではない」という考えは捨て、小さなことでも積極的に伝えること。むしろ、小さなことほど他の人からはなかなか言われる機会がありませんから、それを伝えることで「こんなところまで見てくれているんだ」と、あなたへの信頼感が強まるでしょう。
2:安心感、肯定感を与える
「心理的安全性」「自己肯定感」という言葉をよく聞くかと思います。自分の存在を認められている、必要とされていると感じられる環境に身を置くことで、人は十分に実力を発揮し能力を伸ばせるのです。そうでない環境では活躍できないばかりでなく、優秀な人ほど適切な居場所を求めて去ってしまいます。人材の能力開発や定着促進の下地づくりとして、社員が安心感と肯定感をもって働ける環境を醸成することはマストと考えてください。
ではどうすればいいのでしょうか。一回何かをしたからといって効果が長続きするものではありません。日々継続すると効果的な小さな取り組みを4つ紹介します。
名前を呼ぶ
心理学で「ネームコーリング効果」と言われますが、人は自分の名前を呼んでくれる相手に対して好感を抱きやすい現象があります。「どう思う?」ではなく「〇〇さんはどう思う?」のように、相手の名前を口にしなくとも会話が成立するような場面でも敢えて意識して呼ぶようにしてみましょう。
挨拶にひとこと付け加える
朝や退勤時の挨拶に、プラスアルファのひとことを付け加える方法です。「おはようございます。昨日の帰りは〇〇に間に合いましたか?」「今日の〇〇は大変でしたね。お疲れさまでした」など、相手の状況に合わせた言葉がけにより定型的な挨拶を脱却できます。これにより部下は「自分のことを気遣ってもらっている」と感じることができるでしょう。
小さなありがとうを重ねる
「書類を作成してくれてありがとう」「昨日は遅かったのに、今日も定時で出社してくれてありがとう」「この仕事を担当してくれてありがとう」など、部下に感謝の気持ちを述べる機会は意外に多いものです。業務上当然のことであっても、部下がしてくれたことに対して小さなありがとうを一日に何度でも重ねましょう。言えば言うほど、部下の安心感と肯定感が積み上がっていきます。
未来の話をする
「来年には〇〇さんと一緒に□□の仕事ができたら嬉しいな」「3カ月くらい経ったら〇〇さんに□□を任せたいと思っています」のように“未来に自分がいる前提”の話をされると、人は「自分は必要とされている」と感じられるものです。確定した話がなくても、自分の気持ちでかまいません。未来の希望はどんどん話しましょう。
3:自発行動を促す
「最近の若者は受け身だ」と言われることがあります。部下に自ら行動を起こしてもらうには、無理やりさせるのではなく「行動しやすい環境をつくる」ことが重要です。実際、部下と良い関係を築いている上司は、指示や命令はほとんどしていません。ここでは、部下が「やりやすい」「やりたくなる」状況にもっていくための具体的な方法3つをお伝えします。
テーマと方法を限定する
「何でもいいから意見を聞かせてください」と何度も言っているのに声が挙がらない、といった経験はないでしょうか。そのようなときは「〇〇の業務を効率化するための意見を、□日までにこの用紙に記入私の机に置いてください」のようにテーマと方法を限定すると、意外と集まります。
責任の範囲を明確にする
「部下が指示されるまで動かない」「自分の判断で対応してくれない」といった悩みを持つ上司の方もいるでしょう。そのときは「ここまでは自由にやっていい」「ここからは私に相談してから対応してください」と、責任の範囲を明確に示すことが重要です。まず狭い範囲から始め、そして様子を見ながら徐々に広げていくと、少しずつ自分の判断で行動できる人材に育っていきます。
結果に関係なく褒める
どれほど小さなことでも部下が自分から行動した時、自分の判断で対応できた時は、そのこと自体を結果に関わらず褒めてください。慣れないうちは失敗することもあるかと思いますが、だからといってすべてを否定してしまうと、その部下はもう二度と自分から行動しなくなります。部下から信頼を得ている上司は、結果についてフィードバックすることとプロセスを認めて褒めることを明確に分けているのです。
4:行動を変える指導をする
部下との信頼関係は、良いところを褒めるだけでは築けません。人は、自分が間違いをおかしたときに正しい方向へ導いてくれた人に対して敬愛を抱き、自分を成長させてくれた環境に愛着を感じるものです。
褒めることや受容することは大事ですが、間違っていることに対して指導を行わないと「媚びている」と思われかねません。最近の若者は打たれ弱いなどと言われますが、指導の方法を間違えなければ、部下のモチベーションを下げることなく行動を良いほうへ変えられます。
事実を率直に伝える
部下が明らかに間違いをおかしていたり、良くない行動をしているときは、濁さず「〇〇が間違っています」と率直に言いましょう。このとき、感情や主観を入れずに事実をそのまま伝えるのがポイントです。語気を強くしては威圧感を与えるのでいけませんが、優しく言う必要もありません。淡々と、事務的なくらいでちょうどいいです。
人として尊重する
率直に伝えるべきなのは、あくまでも部下の「行動」が間違っているということです。決して部下の人格を否定する言い方になってはいけません。コツは「部下の行動を主語にする」こと。「〇〇さんは間違っている」と部下を主語にすると部下自身を否定した言い方になりますが、「◇◇したことが間違いだった」と行動を主語にすれば、人格を否定せずとも誤っている事実を伝えられます。
その際「◇◇したことは間違っていたけれど、△△を考えたことはとても良かったですね」というようにプロセスを褒めることをセットにすると、人として尊重する気持ちがさらに伝わりやすくなります。
目先の反応や結果にとらわれない
「部下にこんなことを言ったらどう思われるだろう」「うまくいかなかったらどうしよう」と目先の反応や結果を気にしながらでは、伝えたいことがまっすぐ伝わりません。また、そのようなおどおどした気持ちは相手にも見透かされてしまいます。伝えるべきことをしっかりと準備したら、あとは「結果はどうなっても後悔しない」くらいの気概を持ち、堂々とした心の姿勢で臨むことが大事。そのほうが結果もついてくるものです。
互いの行動を約束する
部下を指導する時「次から気を付けてね」と言っていませんか? 間違いや失敗に対して「気を付ける」という対策法は具体性がなく結果の検証ができないため、実はあまり意味がありません。大事なのは、あくまでも部下の「行動」についてその場で約束すること。例えば書類の記入ミスなら「書き間違えないように次から気を付けよう」ではなく「間違いを防ぐため、記入したら提出前に同僚とダブルチェックをしよう」ということです。
このとき「ダブルチェックの時間がとれるように業務をフォローしますね」「私もこれまで以上に慎重にチェックするから、一緒にミスを撲滅していこう」のように、部下本人だけでなく上司がしてあげられる行動もセットで約束するとより良いでしょう。
最後に
今回は部下が辞めない上司が身に付けている4つのコミュニケーション術を紹介しました。
一つひとつの行動は小さくても、積み重ねることで数か月後、1年後には「部下が辞めない上司」になっていることでしょう。結果は後からわかることですが、行動は今すぐできます。ぜひ今から始めてみてください。
今回お伝えしたようなこと以外にも「社員とのコミュニケーションに悩みがある」という経営者の方がいらっしゃいましたら、佐賀県よろず支援拠点へお気軽にご連絡ください! 国が運営している機関のため、相談は何度でも無料です。
詳しいご利用案内はコチラから
https://yorozu-saga.go.jp/yorozu